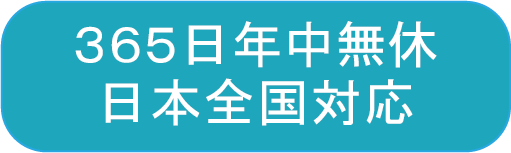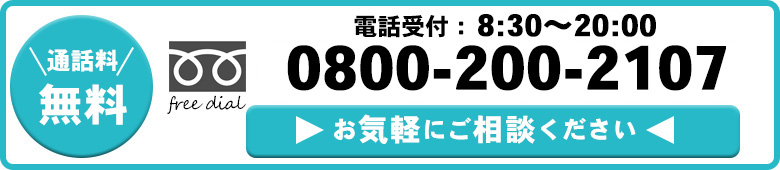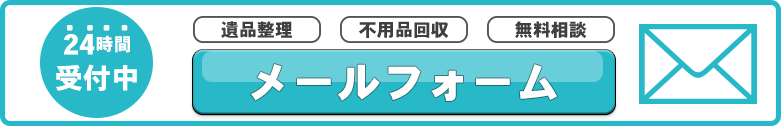実家が汚い5つの原因|帰りたくないときの対処と片付けのコツ

自分や義両親の実家が汚いので、毎年帰省するのが憂鬱な方もいるのではないでしょうか。実家が遠方の場合には泊まることにもなり、布団や食器、お風呂等の衛生面も気になりますし、子供がいる時にはさらに神経を使います。
汚い実家に住むことはリスクを抱えて生活することでもあります。
この記事を読むと実家が汚い事のリスクが分かり、親も自身もストレスがなくなります。
![]()
【監修】遺品整理士協会認定 遺品整理士
片山 万紀子
祖父の遺品整理をきっかけに遺品整理や不用品回収に興味を持ち、遺品整理士協会認定・遺品整理士の資格を取得。ReLIFE(リライフ)のディレクターをする傍ら、年間600件以上の遺品整理に携わる。遺品整理を通して「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとしています。
目次
実家が汚いと感じた5つの理由

実家や義実家の汚さにストレスを感じる方は多いです。
特に自分が1人暮らしや結婚を機に実家を離れ、客観的に見ることができるようになると、実家のモノの多さ・汚さに嫌悪感が増してきます。
この嫌悪感には2つのケースがあります。1つ目は自分が実家を離れている数年の間に実家が汚くなったケース、そしてもう1つは、実家に変化はないものの、自分をとりまく環境の変化に自ずと感じ方が変わったケースです。
1.親の体力が衰えているから

実家が汚くなってしまった理由では、両親の年齢と共に少しずつ掃除や片付けが行き届かなくなってきたことが挙げられます。
年齢が上がるにつれて、足腰が衰えて階段を上ることの負担は増しますし、目も悪くなるので汚れにも気づきにくくなります。
例えば、階段の上り降りがおっくうになり、2階へ行く事が減ったため、ホコリや汚れに気づかず、掃除が行き届かないケースです。
家が徐々に汚くなった場合、住人である両親は気づいていないことも多く、子供から言われてショックを受けることもあります。
両親のどちらかが一人暮らしになったときには実家の汚れ具合は加速していきます。
多少散らかっていても、指摘してくれる人もいなくなりますし、家事全般を一人でこなさなければならなくなるからです。
片付けられない原因は【片付けられない3つの原因とタイプ別解決策―共通点と病気の可能性】をご覧ください。
2.結婚して自分の感覚が変わったから

実家は何も変わっていなくても、自分自身の価値観の変化で帰省した実家を汚く感じることもあります。特に産後の女性は赤ちゃんを守るために、汚れや雑菌に敏感になりやすく、汚く感じてしまう傾向にあります。
結婚してパートナーがキレイ好きだった場合も、その環境に慣れてしまうと、無意識のうちに比較し、実家が汚いと感じます。
例えば、マンションの共有部分は管理費によって定期的に清掃されるため、手入れの行き届いていない実家の外観の汚れが気になってきます。
この感覚は親元を離れ、自分の価値観が変わったことによるものです。
3.世代間による違い
モノに対する価値観は、世代によって異なることも関係します。
戦中戦後の苦しい時期を経験した高齢者は、モノをとても大切にし、執着も強いです。
そして、戦後を生き抜いた彼らの子供にあたる50〜70代は「捨てる=勿体ない」と親からしつけられ、モノを捨てることに罪悪感を覚えます。
行き過ぎた「もったいない」精神から結果的にモノが増え、家が汚くなる要因となるのです。
一方、20〜40代は「断捨離」「ミニマリスト」という言葉が身近で、必要ないものを手放すことに抵抗がありません。衛生面の考え方や、許容範囲も世代によって異なります。
実家の状態は変わらなくても価値観が変わったため、実家が汚くなったと感じてしまいます。
4.セルフネグレクトになっている
ご両親のどちらかがエルフネグレクトになっている可能性も考えられます。
セルフネグレクトになると自分自身のことに無関心なるのが特徴で、身の回りのことすらできない状態です。
たとえば
・お風呂に入らない
・食事も十分にとらない
・体調が悪くても病院に行かない
など自身の健康管理すらおろそかになってしまい、とても部屋の掃除どころではなくなっている状態です。
5.親の判断能力が鈍化している
親の判断能力が低下していることも、実家が汚くなる原因の1つに考えられます。
一般的に50歳を超えると徐々に認知機能は低下するといわれています。
認知機能の中でも片付けに必要な
・遂行力
・判断力
・記憶力
の3つは50歳あたりから緩やかに低下していくものです。
掃除を始めるための思考がなければ、たとえ体力があったとしてもゆるやかに実家は汚くなってしまいます。
実家が汚い4つのリスク
実家が汚いと「怪我」「病気」「人間関係」のリスクがあります。どれも初期段階であれば対処法が取れるものです。
1.怪我をしやすい

汚い実家はモノが多く、モノが床に直置きされていることが多く、つまずいて転倒する可能性が高くなります。
平成22年の内閣府調査では「自宅内で転倒したことがある」と回答した高齢者は9.5%でした。そして転倒した高齢者の3人に2人は、打撲やすり傷、骨折など何らかの怪我をしていると回答しています。
高齢者は骨折すると治りが遅く、最悪の場合、歩けなくなる恐れがあるため注意が必要です。
また、頭上の高いところにあるモノは落ちてきてケガをする恐れがあります。
床にモノがあれば地震の時に避難するルートがふさがれ、火災の場合は燃え移り延焼を引き起こす危険性があります。
2.体調不良につながる

家が汚いと、体調不良につながります。
ホコリ、害虫のフンや死骸が空気中に舞い上がると、アレルギーやぜんそくなどの原因になります。また、ダニに噛まれると発疹やかゆみ、皮膚病の危険性があります。
モノが多いと休憩をとる場所がソファやベッドなど狭いスペースに限られてしまいますので、身体的な疲れも取りにくくなります。さらに、どこを見てもモノが目に入るので休まる暇がありません。その結果、疲れやストレスが溜まり、ネガティブな感情に陥りやすくなります。
ネガティブな感情はうつ病やセルフネグレクトにつながるため早めに対処する必要があります。
住んでいる両親はもちろん、遊びに来る孫や子供にも影響があり、特に免疫力のない幼児はアレルギーの発症をしやすくなります。
セルフネグレクトの詳細は【セルフネグレクトの原因と対策方法・コロナの影響は】をご覧ください。
3.親族・友人と疎遠になる

実家が不衛生な環境になると、子供や孫が寄り付かなくなってしまいます。また、友人を招き入れる機会も減るので疎遠になっていきます。
モノが多いと管理が行き届かなくなり、モノを無くしやすいです。これは自分のモノだけでなく借りたモノの場合、信頼を失うことにもなりかねません。
家が汚いと間接的につながりを失うため、孤立しやすくなり、最悪の場合、孤独死を迎えることもありうるのです。
孤独死で発見された場合には親族の心にショックを与えるだけでなく、遺品整理時には特殊清掃費がかかり経済的負担も増します。
孤独死の詳細は【孤独死の処理が自分でできない理由と発見後の手続きと費用】をご覧ください。
特殊清掃の詳細は【特殊清掃と遺品整理・賃貸物件の場合の費用】をご覧ください。
4.結婚の障害になる
実家の汚さが原因で子供の結婚が破談になるリスクもあります。
結婚のあいさつではお互いの実家に挨拶へ行くのが一般的です。パートナーの両親を実家に招き入れる風習のある地域もあります。
実家の部屋を目にしたパートナーが、相手との将来を想像して結婚に踏み切れなくなることも考えられます。
結婚後、孫を見せに行くことまで想像したパートナーは結婚生活にも不安を感じるでしょう。
実家を片付ける4つのコツ

実家の片付けは4つのコツがあります。このコツを押さえておけば、片付けを円滑に進める事ができます。
今すぐに実家を片付けることが難しくてもコツを掴んで根気よく、行動していくことで実家の汚さは解消されていきます。
1.親の説得に時間をかける
実家の片付けでは親に自主的に動いてもらうことが欠かせません。
親が納得している片付けは「進むスピード」も「片付けの完成度」も格段に上がります。。
一時的な片付けは本当の意味での解決策にはなっていません。
あなたが帰った後で、3か月もすれば元の散らかった実家に戻ってしまうでしょう。
本当のゴールは永続的に片付いた状態がキープでき、親が快適に過ごせることです。
説得のポイント
・リスクを理解してもらう
・メリットを共有する
・感情的にならない
・否定的な言葉を使わない
子どもを説得するように、気長にやさしい言葉で説得を続けましょう。
一度でもへそを曲げてしまったら、その後の説得には倍時間がかかるからです。
2.「捨てる」を強要しない

両親の持ち物に「捨てる」を強要してはいけません。
親世代は捨てることに罪悪感を覚えること多く、60年以上かけて作られてきた価値観を変えることは無理です。
また、位置を変えることも両親が拒むのであれば、避けた方が実家を片付けやすくなります。
例えば、玄関に飾ってあった置き物を押し入れに入れることは捨ててはいなくてもおすすめできない方法です。
両親にとっては見慣れた室内であり、そこにあることで心を落ち着かせていることもあります。
親と自分とはそれぞれ別の価値観を持っています。
そして、持ち主である親にしかわからない思い入れがあることを理解することが、実家の片付けには欠かせません。捨てるのではなく「片付ける」「掃除する」を意識しながら実家を片付けていきます。
3.一緒に実家を片付ける

実家片付けは、できるだけ親と一緒に片付ける事が大切です。
実家も家の中に置いてあるものも全ては親の持ち物です。どのような環境になっていようと、親の自由にしてよい家です。
自分が指図され、作業する側になる気持ちで進めましょう。
例えば、「2階の押し入れにあるダンボールをとってくる」「タンスを処分場に捨てに行く」「買取業者に連絡する」など細かい連絡から体力仕事まで引き受けましょう。
また、動くことが億劫になり掃除が行き届かなくなって汚くなっているケースもあります。特に力仕事や細かい作業、根気の入る作業は率先して行うことを心がける事が実家を片付けるコツです。
4.小さな一区画から片付ける

最初は小さな一区画から始めると効果が分かりやすいので、両親も自分も飽きることなく進められます。
特に水回りのキッチンやお風呂、トイレなど効果が目でみてわかりやすく、片付けから掃除まで数時間で終わるのでおすすめです。
押し入れは洋服や写真など複数のモノが入っている上、布団などはすぐに処分できないので、徐々に進めていきます。
実家が汚くなってから半年以上過ぎている場合は片付くまでには最低でも数日、週に1回程度しか通えない時には3か月以上かかることは覚悟しておく必要があります。
また、高齢者は急激な変化を嫌います。小さな一区画を掃除し、親にキレイな状態を実感してもらうことでモチベーションを維持できるよう促すと流れるように実家が片付いていきます。
実家の片付けの詳細は【実家の片付けの6つのコツと片付け業者を利用する目安】をご覧ください。
汚い実家を片付ける準備

4つのコツを理解できたら、実家の掃除を始めます。
親の持ち物である実家をキレイにするには、もちろん親の了承は必要です。
「捨てる」ではなく「片付ける」「掃除する」ことに重点を置きます。
汚さを判断する
実家の汚れ具合を判断することが第一歩です。
自分たちだけでは片づけられない状況では業者の手も借りなければ片づけることができないからです。
自分たちで片づけられる実家
・片付いていないのは3部屋以内
・3名以上片付けに協力してくれる人がいる
・朝のゴミ出しを手伝える
上記3つのポイントをすべてクリアできていれば自分たちでの片付けができます。
意外と重要なのが、朝のゴミ出しを手伝えることです。
親世代にとっては「ゴミ出しに行くこと」も高いハードルとなっていることがあります。
右から左へゴミを寄せるだけではなく、適切に処分することまで手伝ってあげられることは大切です。
実家を片付ける計画を立てる

実家を掃除する際、作業が中断しないように事前の下準備を行うことが重要です。
数か月位以上かけて汚くなった実家を清潔な状態に戻すには、同じくらいの時間が必要なので、計画的取り掛かると挫折しにくくなります。兄弟、姉妹も協力してくれる時には計画の中に人数も入れましょう。
人手は多い方が早く片付けられます。
例えば、「5月中にキッチンとトイレ、洗面の物を整理して、カビや汚れを落とす」の様にいつまでにどこまで終わらせるかを具体的に決めると達成感も味わえます。
また、「お盆や正月など親族が集まる日までにリビングとキッチンを掃除する」のように期日が決まっているときには目的や場所が明確になります。
実家のゴミの処分方法を知る

実家を片付ける時にはゴミが大量に出る事が想定されるので、自治体のゴミ収集日と分別ルールを調べるとスムーズに処分できます。
両親がゴミの分別やゴミの回収日について疎いときには自治体のホームページで確認しましょう。自治体のホームページはゴミの収集について小さくしか書かれていないこともありますが、ポータルサイトよりも最新の情報が掲載されています。
平日・休日関係なく実家の片付けができるのであれば、可燃ゴミの前日に作業するとゴミの処分までがスムーズに進めることができます。
掃除道具と材料の準備

掃除道具やゴミ袋も事前に準備しておくと当日の作業がスムーズです。
掃除道具が実家にある場合が多いので、消耗品だけを準備して持ち込みます。段ボールやガムテープなど必要になるか分からないものは必要になってからで構いません。
【片付けに必要な物】
・マスク・ゴム手袋・可燃ゴミ袋・雑巾・洗剤・殺虫スプレー
雑巾を買う場合は実家に保管されている布類を確認しましょう。
モノを大切にする親であれば、もらい物のタオル類、特に社名入りのタオルや手ぬぐいなどが袋に入ったまま大量に保管されている可能性が高いです。
雑巾がわりのウエスとして活用することもおすすめです。「いつか使う」と捨てることを拒否する親も「掃除に使って良いか」と聞けば、了承を得やすくなります。
実家を片付け、掃除する

準備が整ったら、実家の片付けや掃除を進めていきます。
ゴミ・不用品を捨てる
実家が汚い原因となるゴミや不用品を捨てることから始めます。
捨てる基準は「親が捨てたいと思うもの」と「親が納得するもの」で、賞味期限切れの食品などが当てはまります。自分から見てゴミであっても、親が「何かに使える」と言って残したいと言う場合は、説得やこっそり処分することは避けます。例えばクッキーの缶やジャムの空き瓶は、「まだ何かに使えそう」と感じ、親から許可をもらう事が難しいです。キレイな状態であればそのままで良いでしょう。
迷う時には保留する
処分が進まないモノは、保留にして活用しつつ、徐々に処分するのも一つの方法です。
例えばクッキーなどの缶容器は、捨てる機会が限られた古い電池や刃物などの一時保管場所として再利用できます。
小さなものや他人から見ればゴミでも「捨てる」ことは親世代にとって想像以上にハードルが高い作業です。捨てることにためらうモノは「保留」とするところから始めると片付けやすくなります。
ゴミ、不用品を捨てる時の注意点
親が捨てると決めたものは自治体のルールに従って分別して捨てます。
可燃ゴミ、不燃ゴミ、リサイクル資源、粗大ゴミが一般的ですが、分別のルールは自治体によって異なります。
一般的に1度に出せるゴミは45Lの袋2〜3袋までが目安で、ルールとして定めている自治体もあります。1度に大量のゴミを集積所へ出すと、収集車が運び切れない・通行の妨げになるなどの迷惑がかかります。ゴミの量が多い時は数日に分けて出すか、自治体のゴミ処理場へ直接持ち込んで処分する方法もあります。
実家の収納を整える

ゴミや不用品の処分が落ち着いたら、収納を整えていきます。
収納家具からモノがあふれていても、整頓すれば収まることもあるので、親が捨てられない場合や物が多くても収納できることもあります。まずは収納家具の中をすべて出してから整えると両親も忘れていた服が出てくることもあります。
服は使用頻度や種類に分けて、同じ大きさに畳むだけでも収納できる枚数が増えますし、使い勝手もよくなります。また、大きさを揃えることは服以外でも見た目がすっきりするのでおすすめです。
例えば、本なら高さや大きさを分けて揃えて収納したり、背出しの色を揃えたりする収納もあります。
定期的に掃除や片付けができない時にはクローゼットに防虫剤や除湿剤を入れ、衛生的に保管しましょう。モノに住所を決めてあげると実家は片付けやすくなります。
片付け業者に依頼する

自分たちで時間が取れない時や、親が拒否する場合は、第三者である片付け業者を利用する方法もあります。
依頼する範囲や規模によって、生前整理業者や不用品回収業者、家事代行サービス、整理収納アドバイザーなど専門業者や専門家がいます。
身内の言うことは聞かなくても、専門家の意見であれば耳を傾ける方も多いです。
実家の片付けを業者に依頼した時の費用

モノが多くて汚い実家を片付け業者に依頼した場合の費用は10万円以上かかります。
広さや間取りが違っても、ゴミの質や量によっても異なります。例えば、床が見えないほどモノにあふれていれば高くなります。一方、モノがそれほど多くない、ゴミより大型家具の処分や買取可能なモノが多く含まれている場合は、処分費用を抑える事が可能です。
| 広さ | 費用の目安 |
| 1K〜1R | 10〜30万円 |
| 1DK〜3LDK | 10〜40万円 |
| 4DK〜 | 20万円以上 |
実家の片付けを業者に依頼する時の注意点

実家の片付けを業者に依頼する前に必ず、親の同意を得ましょう。可能であれば業者選びから見積もりの立ち合いなど全て一緒に進めていく方が、片付けを進めていく中で親の意見を尊重できます。
また、片付け業者は実家の汚さレベルに最も合う業者を手配しましょう。
モノが多くて足の踏み場もない時は不用品回収業者や生前整理業者など物の仕分け、分別から処分までできる業者を選びます。
モノは多くないが収納が少ない時や出したものをしまうのが苦手な方は家事代行サービスなど整理や収納に特化した片付け業者を選ぶと継続的に依頼できるので、元に戻る心配が少なくなります。
掃除が苦手な場合や時間が取れない方にはハウスクリーニングサービスも提供している業者を選ぶと1つの窓口で完結できます。
不用品回収業者で片付けた後で家事代行サービスを利用するなど併用して利用する方法もあります。
片付け業者の選び方

片付け業者は親と一緒にパンフレットやサイトを確認して、親が納得いく片付け業者を選びましょう。アドバイザー的な立場でそれぞれの業者のメリット、デメリットを伝えるのは構いませんが、自分の意見を押し付けないよう心がけます。
不用品回収業者や遺品整理業者に依頼する時には、「古物商許可」や「一般廃棄物収集運搬許可」を取得している業者を選ぶと、不法投棄の心配がありません。
生前整理業者の選び方の詳細は【遺品整理業者の選び方・失敗しない3つのポイントでトラブル回避する】をご覧ください。
汚い実家に泊まりたくない|2つの対処法

汚い実家や義実家に帰省したくない時の対処法についてご紹介します。
実家を片付けるには親を説得することが欠かせませんが、説得には時間がかかることも想定されます。本項は応急処置としての方法です。
1.両親を招待する
自分たちの家に両親を招待するのも一つの方法です。
マンションなどで両親が泊まる部屋がない場合は、寝る時だけ近場のホテルを手配すれば、お互いにストレスなく滞在する事ができます。
自分たちの住む家をみて、自分の家が汚かったという気づきと危機感により、片付けに前向きになることも期待できます。
2.旅行や食事など代案を提案
旅行や一緒に食事をするなどの代案を提案し、実家への帰省を避けるのも一つの方法です。
お互いの家ではなく、中間地点や全く別の土地へ旅行する。もしくは、近くに住んでいるのであれば、一緒に外食するなどの代案を提案するのもよい方法です。
これらは、親も自分たちもホスト側となって相手をもてなすストレスがありません。
その他、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、テレビ電話などで顔を合わせるように変更することもおすすめです。パソコンが苦手な世代でもLINEアプリを使えばボタン一つで顔を見ながら話すことができます。
実家が汚いと遺品整理がつらい

遺品の量は遺品整理の辛さや負担に直結し、多ければ多いほど、遺族にとって心と身体に負担がかかります。
実家にあるモノは両親がいなくなったあと遺品へと変わり、子供や配偶者が相続人として引き継ぐことになります。モノが多ければ多いほど、仕分けや処分に時間と体力・お金が必要になり、遺品整理の大変さは増してきます。
遺品整理の負担を減らすためにも、両親が元気なうちから生前整理や老前整理を進めることが推奨されます。
遺品整理がつらい理由は【遺品整理がつらい3つの理由と悲しみを乗り越えた方法】をご覧ください。
親の遺品整理の進め方は【親の遺品整理のコツとやり方5ステップ・できない時の対処法】をご覧ください。
老前整理を勧める
老前整理とは、老いる前に身辺整理を行うことを指し、40〜60代に始めるといいと言われています。
老後に必要な生前整理を軽減する、生活環境を快適にする、そしてなによりも子供の世代も若く、協力を得やすいことがメリットです。
老前整理をしておくと、身の回り環境はもちろん、人間関係もすっきりするので趣味やセカンドライフをより楽しめるようになります。
老前整理の詳細は【老前整理を成功させる3つのコツと失敗する3つの原因】をご覧ください。
生前整理を勧める
生前整理とは自身が亡くなった後、遺された家族が困らないように身の回りの整理を行う事を指します。怪我や病気で自分の身体の自由が利かなくなったなど、もしもの場合に備え、遺されたモノを遺品として引き継ぐ子供の負担を軽くする効果があります。
生前整理の捉え方は伝え方を間違えると、大きな溝を生むことにもなりかねません。親が生前整理の本質を捉えていない時には「死ぬのを待っているのか」と憤慨する可能性もあります。
老前整理や生前整理という言葉を避け、「転倒やケガをしないよう、一緒に片付けよう」と働きかけるのも一つの方法です。
親が死ぬのを待っているのではありません。この家で、安全で快適に過ごして欲しいと願っての片付けであることを伝えれば理解してくれる可能性が高いです。
生前整理の詳細は【生前整理で5つのやることリストー自分のためと家族のために始める時期】をご覧ください。
実家が汚い時の対処法まとめ
・実家が汚いのは2パターンで、1つ目は自分が実家を出てから汚くなったケース、2つ目は自分の感覚が変わったケース。
・実家が汚いと人間関係や健康面でリスクがある
・実家を片付ける時には計画的に、親の意見を尊重して行う
・実家の汚れ具合がひどい時や、説得に応じない時は片付け業者を利用する方法もある
・両親を自宅に招いたり、旅行に行くなど、実家に帰省せずに両親と会う方法もある
テレビ|洗濯機|冷蔵庫|マッサージチェア|ベッド|学習机|電子レンジ|座椅子|プリンター|炊飯器|物置|消火器|畳|カーペット|日本刀|布団|自転車|本|金庫|カラーボックス|衣装ケース|スーツケース|婚礼家具|家財整理|ぬいぐるみ|物干し竿|毛布|食器|位牌|エレクトーン|灯油|家具|扇風機|ゴミ箱|トースター|チャッカマン|スプレー缶|マニキュア|発泡スチロール|ハンガー|カーペット|鏡|ゴルフバッグ|フライパン|ガスボンベ|ガスコンロ|ビーズクッション|土|コーヒーメーカー|ウォーターサーバー|靴|保冷剤|ヘアアイロン|ライター|タンス|室外機がうるさい|ペンキ|体重計|石油ファンヒーター|タイヤ|